素人感覚でこの人のピアノはJAZZなの?と思う時もあるけど良いのである(笑)
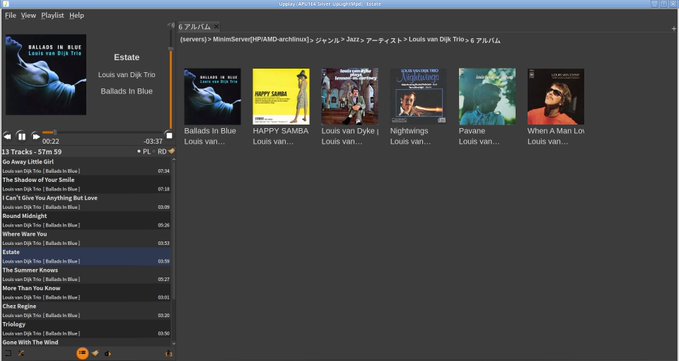
2026/2/18
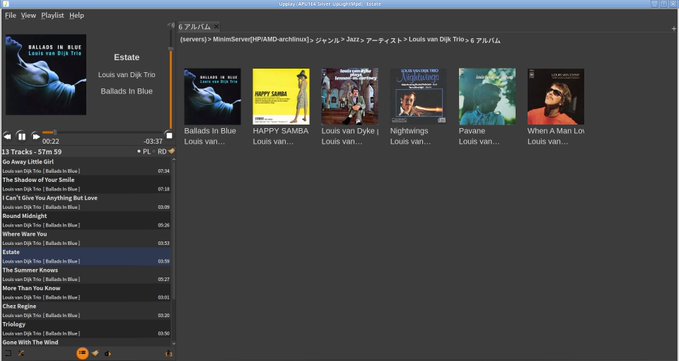
— posted by くま at 09:15 pm
2026/2/12
— posted by くま at 07:18 pm
2026/2/11
— posted by くま at 03:15 pm
2026/2/9
— posted by くま at 09:16 am
2026/2/8

— posted by くま at 09:13 pm
2026/2/5
— posted by くま at 03:27 pm
2026/1/31

— posted by くま at 12:11 pm
2026/1/11
— posted by くま at 10:20 am
2026/1/8
— posted by くま at 12:08 pm

— posted by くま at 01:14 am
Comments